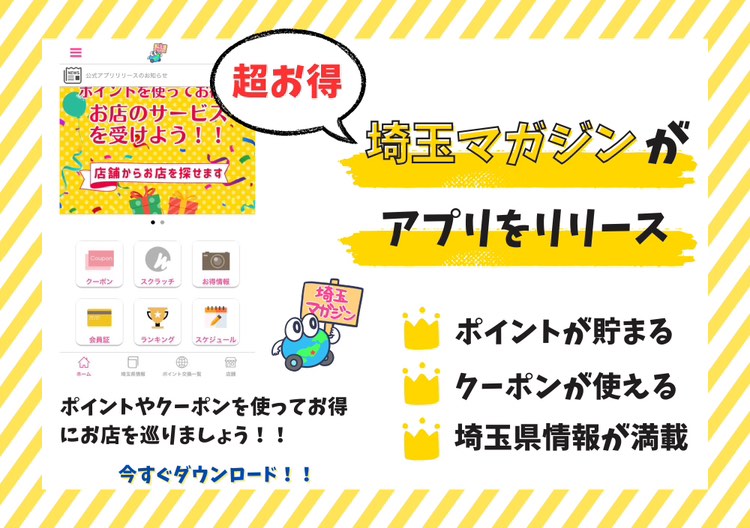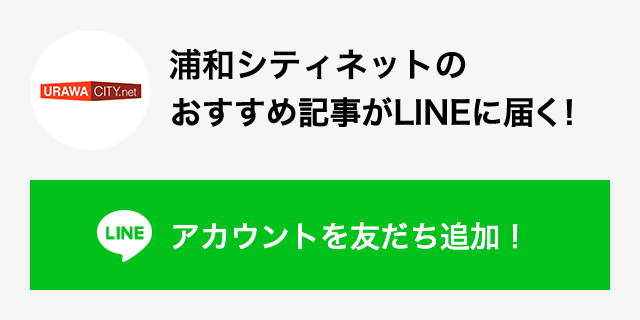桜区田島にある「御嶽(おんたけ)神社」は鎌倉時代の永仁3年(1295年)に創建したと伝えられている神社です。
他にも御嶽神社という名前の神社があるので「田島御嶽神社」とも呼ばれています。
木曽御嶽山 普寛行者修行の地「御嶽神社」

御嶽神社は西浦和駅から徒歩6分の場所にあり、武蔵野線の近くの住宅街にたたずんでいます。
長野県と岐阜県にまたがる木曽御嶽山の王滝口(おおたきぐち)を開いた、秩父生まれの普寛行者(ふかんぎょうじゃ)が御嶽神社で根本修行をしたと伝えられています。
御嶽神社の社殿は全て朱色と白で塗られていてとても綺麗です。
御由緒
本神社は人皇第92代伏見天皇の御代永仁3年4月(鎌倉時代)御創建されたと伝えられております。古社にして、木曽御嶽山王滝口開祖普寛行者が天明年代(江戸時代)本神社に於いて根本修行したと伝えられております。
普寛行者が木曽御嶽山王滝口開山という偉業を成し遂げた後の全国巡教の折、本神社で参拝修行をなされ、木曽御嶽神社の御分社として奉祭し、その時開山御禮に神納された掛軸(さいたま市指定有形文化財)を現在社宝として御守りしております。
本神社の崇敬は高く、信仰は広く、尊仰の中心となっております。
引用:御嶽山公式サイト
拝殿と本殿

こちらが拝殿。

立派な彫刻です。

賽銭箱の真上には白龍彫刻というとても迫力のある彫刻があります。
木曽御嶽山、三ノ池の白龍大権現を勧請し、厄除開運、身体健康、病気平癒、火盗除けの御神徳があるとされます。一枚板の檜で、直径150cm厚さ15cm重さ80㎏。賽銭箱の上から見上げる、迫力のある白龍彫刻は一見の価値があります。

拝殿前の鳥居には雷鳥。
木曽御嶽山開山の途中、道に迷った普寛行者を頂上まで道案内したとされる雷鳥を、本神社では神使として天神雷鳥大神をお祀りしております。

拝殿奥の本殿。
さいたま市指定天然記念物 御嶽神社のイヌマキ

このイヌマキは、目通り幹回り1.5m、高さ11~12m(平成6年測定)で、地上2mのところで幹は二つに分かれており、東側の幹は約3mのところで折れ、主幹は西側の幹となっています。イヌマキは雌雄異株であり、この木は実がつかないところを見ると、雄株と考えられます。樹齢350年程といわれるかなりの古木にもかかわらず、樹勢は旺盛で、樹形も優れており、保存価値の高い樹木といえます。
摂末社やその他の建造物
伏見稲荷社(宇迦御魂命:五穀豊穣・商売繁盛)

霊神社

天神雷鳥社

天神社(学問の神 菅原道真公)

霊神碑

手水舎

他にもゑびす大黒天(福徳円満の神)があります。
御朱印もいただけるようです。
田島 御嶽神社
| 住所 | さいたま市桜区田島3-28-30 |
|---|---|
| 御祭神 | 國常立尊(萬物創造神、五穀豊穣、無病息災) 大己貴命(身体健康、福徳円満) 少彦名命(病気平癒、長寿) 猿田彦大神(交通安全) 天鈿女命(芸事の神) |
| 相殿 | 八海山大神、三笠山大神、意波羅山大神、武尊山大神、天照皇大神、鎮守産土大神、天地神祇八百萬神 |
| 駐車場 | 有り |
| 公式サイト | 御嶽神社 |